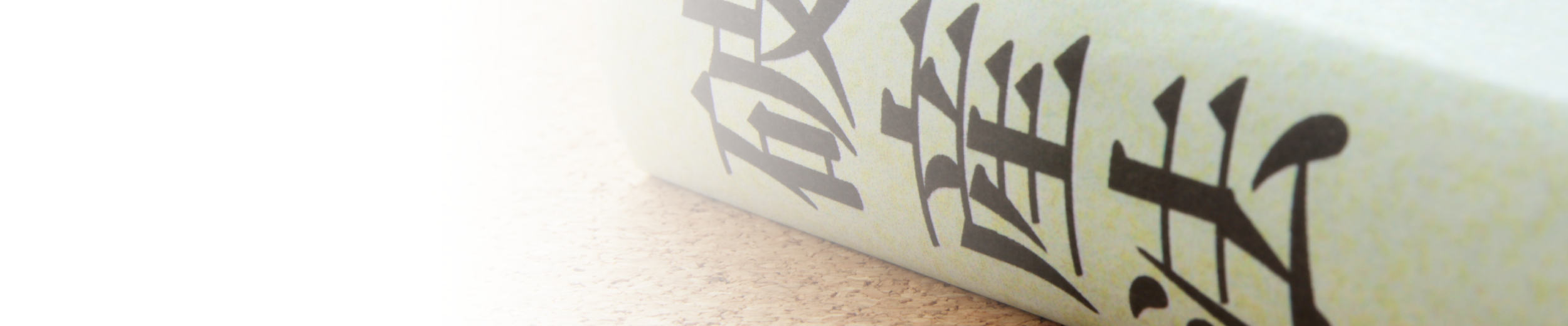
借金・債務整理
Debt Consolidation
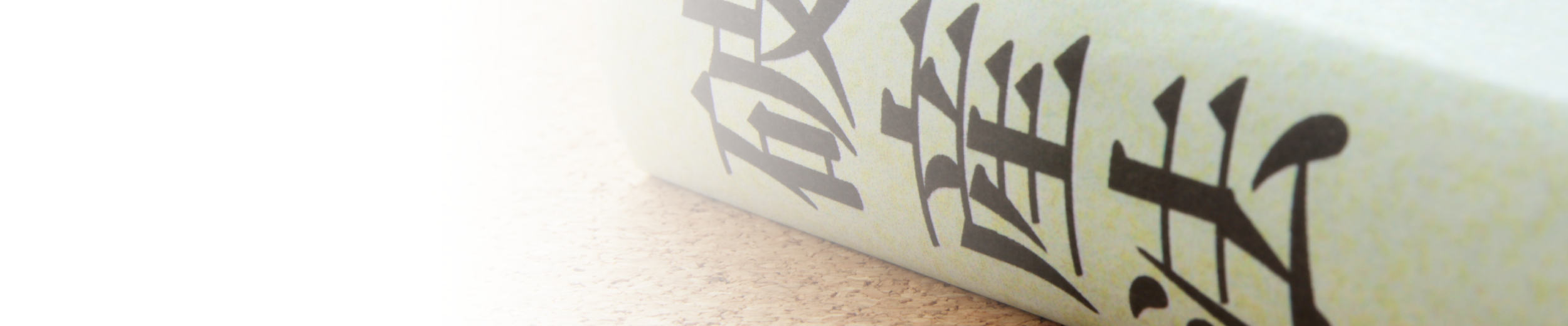
借金・債務整理
Debt Consolidation
初回60分無料。2回目以降30分5,000円(税別)
詳細な内容につきましては、各タイトルをクリックして頂くとご覧頂けます。
【過払い金返還請求】
【任意整理】詳細はコチラ→
【個人再生】詳細はコチラ→
【自己破産】詳細はコチラ→
※個別事情によっては、上記以下の金額でお受けできることもあります。
また、分割払いにも対応できますので、お気軽にご相談ください。
代表的な債務整理手続である『任意整理』・『個人再生』・『自己破産』の三種類について、簡単にご紹介致します。
どの手続を利用できるのか、どの手続きを利用するのがベストなのかについては、個別の事情により異なりますので、弁護士にご相談ください。
弁護士が裁判所を通さず各債権者(金融業者)と直接交渉をする債務整理方法です。ほとんどの場合で、将来利息がカットされ、3年から5年の長期分割返済が実現できます。
多額の借金につき返済が困難な状況にある個人が、将来継続的に収入が見込まれる場合に、その借金の一部を一定の額、一定の期間で支払う(この計画を再生計画と言う)ことにより、残りの返済の免除を受けられるという手続きです。
| 個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、どちらも大まかに言うと多額の借金がある個人が返済困難な状況にあるが、将来継続的に収入が見込まれる場合に、その借金の一部を一定の額、一定の期間で支払う(この計画を再生計画と言う)ことによって、破産することなく残りの返済の免除を受けられるという手続きです。 また、個人再生では住宅ローン特則というものを利用すれば、住宅を手放さずに(住宅ローンの支払いは続けたまま)手続きが出来る場合もあるので、住宅を手放したくない場合には個人再生の利用を検討されることをおすすめします。 小規模個人再生と給与所得者等再生にはそれぞれ下表の様な利用要件があります。 原則として今後継続的に収入が入ってくるのであればどちらでも利用可能ですが、大抵の場合、小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が支払わなければならない金額が多くなるため、小規模個人再生を選択するケースが多いといえます。ただし、給与所得者等再生の場合には、債権者の同意が不要のため、債権者から異議が出されることが予想される場合は、給与所得者等再生を利用するメリットがあるといえます。 【小規模個人再生利用要件】
【給与所得者等再生利用要件】
①借金総額の5分の1(※借金総額が3,000万円以上の場合は10分の1) ②100万円のいずれか多い方の額のこと。 (*2)可処分所得要件とは 1年間あたりの手取り収入から税金や社会保険料、及び最低生活費(最低限度の生活を維持するのに必要な費用)を控除した額の2倍以上であること。 最低生活費は居住地域・家族構成を考慮して政令に基づき算出される。 (*3)清算価値保障の原則とは もし自己破産をしたら換価処分され債権者に配当される全財産、(現金・預貯金・不動産・自動車・保険の解約返戻金・将来受け取る見込みの退職金の一部など)の合計額が支払金額を下回らないこと。 【再生認可要件】 さらに個人再生を利用するには、小規模個人再生・給与所得者等再生ともにその再生計画(借金総額の一部を一定の額、一定の期間で支払う計画)が裁判所により認可される必要があり、この認可を得るには以下の様な要件を満たす必要があります。
|
借金の返済が不能の状態にあるときに裁判所にその旨を申立て、その時所有している全財産を全て現金化して各債権者に分配する制度です。免責を受けることができれば、残った借金は免除されます。
| 自己破産とは、借金の返済が不能の状態にあるときに裁判所にその旨を申立て、破産の宣告を出してもらい、その時所有している全財産を全て現金化して各債権者に分配し、それでも残った借金に関しては免除を受けることができる(これを免責という)制度です。 財産の現金化には、例えば不動産の売却、保険金の解約返戻金(保険解約時に戻ってくるお金)、将来支払われる見込みがある退職金の一部などがあり、これらの財産の現金化・分配といった手続きは、裁判所から選任される「破産管財人」が行います。この場合には管財人費用として20万円から50万円を予め裁判所に納める必要があります。 ただし所有している財産がごくわずかで、特に現金化出来るようなものもない場合は、現金化・分配といった手続きは取らず、破産の宣告と同時に破産手続きの終了(これを同時廃止という)となります。この場合には管財人費用はかかりません。 しかし破産手続きが終了した時点では、まだ残りの借金が帳消しになった訳ではなく、免責の申立て(通常破産と同時に申立て)により、その決定を受けた時点で初めて残りの借金の返済が免除されることになります。ただ、この免責は誰でも認められる訳ではありません。代表的な免責不許可事由は下表の通りです。 【免責不許可事由】
|
